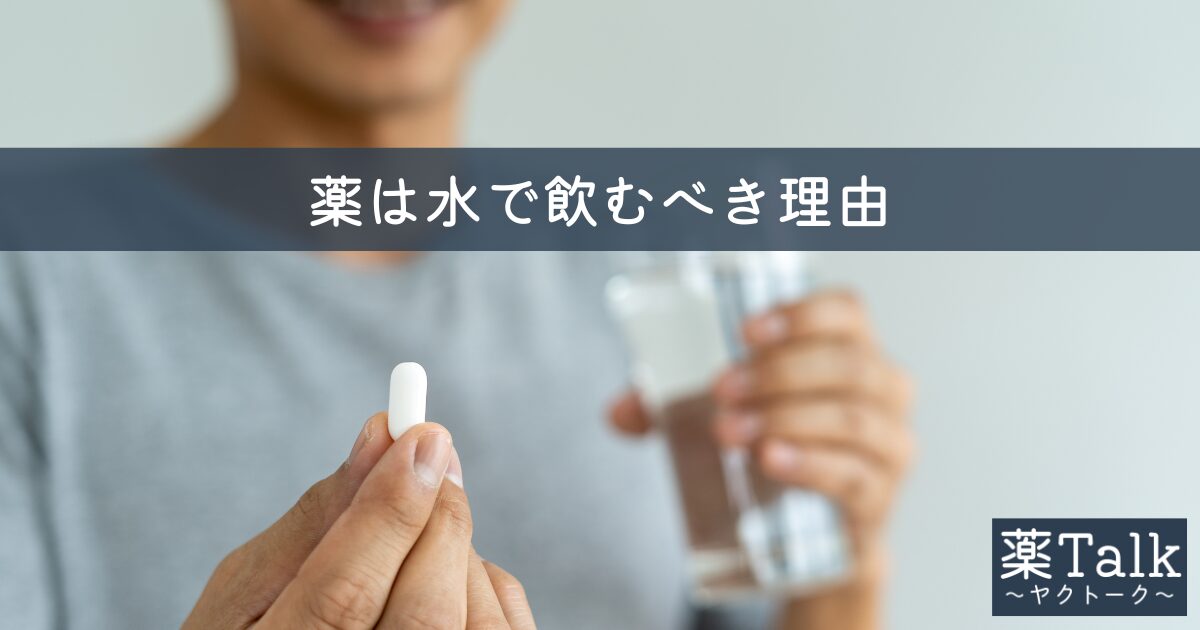こんにちは、「薬Talk」編集長、薬剤師のNoriです。
自分は薬剤師だから、薬の飲み方は完璧――そんな思い込みを打ち砕いた、ある朝のヒヤリ体験を、今でも時々思い出します。
出勤前のバタバタの中、抗菌薬をコップも使わず牛乳で流し込んでしまった私。ふと、「あれ、キレート起きるやつでは…?」と気づいた瞬間の冷や汗。
知識があるからこその油断。そんな“薬剤師あるある”をきっかけに、今回は「薬はなぜ水で飲むのか?」をあらためて確認してみましょう。
服薬指導のときにも、自分自身の服薬にも、役立つ基本の知識です。
目次
薬はなぜ「水」で飲むのが基本なのか?
水は、薬の効果を最大限に引き出し、副作用を抑えるための「最も安全な飲み物」です。薬局でも「水で飲んでくださいね」とお伝えするのは、以下のような科学的理由に基づいています。
✅ 1. 水は薬にとって“中立で安全”な存在
水はpHがほぼ中性で、カルシウムや糖分、タンニンなどの成分も含まれていないため、薬の吸収や分解を妨げることがありません。
一方、牛乳・お茶・ジュースなどには、薬と相互作用を起こす成分が含まれており、効果が減弱したり副作用が強まるリスクもあります。
✅ 2. 多くの薬は「小腸で吸収されるように設計されている」
薬の多くは、胃ではなく小腸で吸収されるように設計されています。
水で飲むと、錠剤やカプセルがスムーズに胃を通過して小腸へ届くため、吸収効率が上がります。
【薬の通過ルートとpH環境】
| 通過部位 | pH値 | 特徴 |
|---|---|---|
| 口 → 食道 | 約6.8 | 酸やアルカリの影響なし |
| 胃 | 1〜3 | 強酸性、薬の不安定性に注意 |
| 小腸 | 6〜8 | 薬の吸収が最も効率的 |
✅ 3. 飲み物によるpHや成分の違いに注意
飲み物の性質によっては、薬の分解や吸収速度、体内動態に影響を及ぼすことがあります。
【飲み物と薬の相互作用例】
| 飲み物 | 注意が必要な薬 | 理由 |
|---|---|---|
| 牛乳 | ニューキノロン系抗菌薬など | カルシウムが薬とキレートを形成し吸収低下(2時間空けるのが理想) |
| グレープフルーツジュース | 高血圧薬・高脂血症薬など | CYP3A4を阻害し血中濃度が上昇する可能性 |
| 緑茶・ウーロン茶 | 鉄剤 | タンニンが鉄と結合し吸収低下のおそれ(食事程度なら問題なしという報告も) |
| コーヒー | 総合感冒薬など | カフェイン過剰摂取や薬の吸収変動に注意 |
💡水分量にも注意!コップ1杯以上で飲む理由
薬が食道に貼りついてしまうと、食道潰瘍や炎症を起こすことがあります。特にビスホスホネート製剤やカリウム製剤などでは重大な副作用のリスクも。
150〜200mLの水でしっかり流し込むことで、安全かつ確実な服薬が可能になります。
☕薬剤師でもやってしまう“水以外での服薬”リスク
忙しい業務の合間や朝の出勤前、「コーヒーしか手元になかった」「牛乳で流し込んでしまった」という経験、薬剤師なら一度はあるのではないでしょうか。
専門知識があるがゆえの「これくらい大丈夫」という油断。でも、日常的な習慣の積み重ねが、薬効や安全性を左右するのです。
だからこそ、患者さんへの服薬指導だけでなく、自分自身の服薬習慣も見直すことが大切です。
🔥漢方薬は「白湯」が良いとされる理由
漢方薬では「白湯(ぬるめのお湯)」での服用が推奨されることがあります。これは、体を温めて胃腸機能を高めることが漢方の効果発現に役立つと考えられているからです。
ただし、日常的に白湯を用意できない場合は、「常温の水」でも十分に代用可能です。
🧠まとめ|たった一杯の水が薬の効き方を左右する
薬の添付文書には「水で飲むように」とあえて書かれていないこともありますが、それは“当然の前提”とされているからです。
水は、薬にとってもっとも相性が良く、人体にもやさしい飲み物。
その一杯が、薬の効果を引き出し、副作用を防ぎ、患者さんの安全につながる――私たち薬剤師にとって、最も基本的で大切な服薬指導ポイントです。
🔗参考文献・出典
PMDA 医薬品添付文書検索
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/
日本病院薬剤師会「薬物相互作用Q&A」
https://www.jshp.or.jp/cont/11/0120-2.html
くすりのしおり(公益社団法人くすりの適正使用協議会)
https://www.rad-ar.or.jp/siori/
※本記事の内容は一般的な薬学知識の解説であり、特定の医薬品や治療を推奨するものではありません。服薬の際は、必ず医師・薬剤師などの専門家の指示に従ってください。