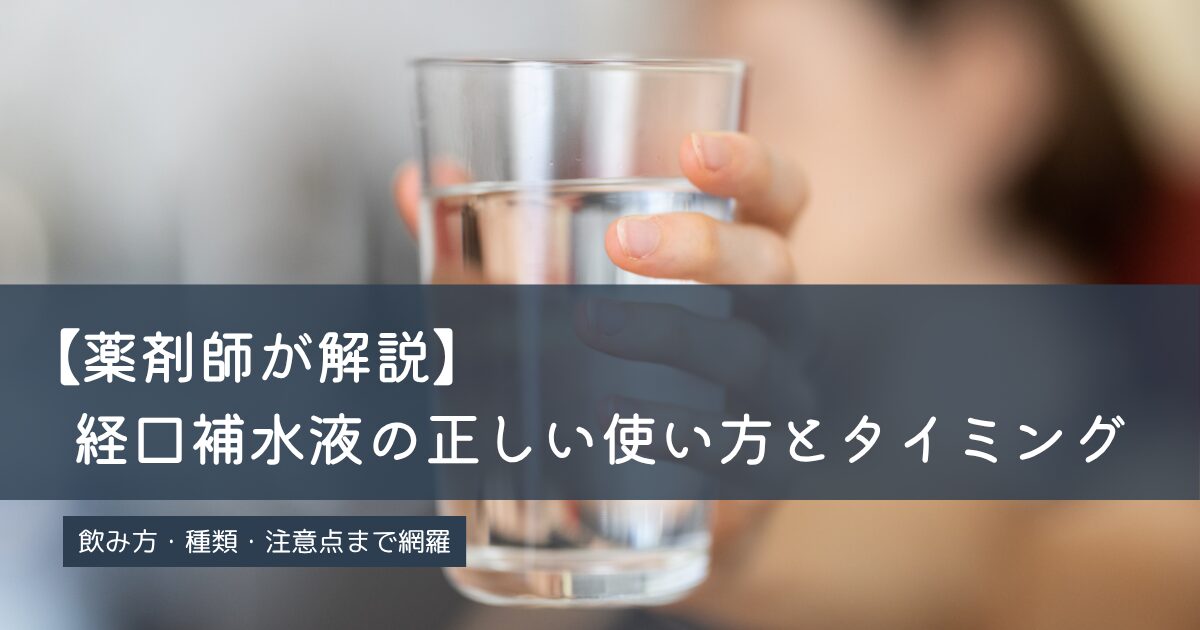こんにちは。「薬Talk」編集長、薬剤師のNoriです。
脱水というと夏の炎天下やスポーツ時をイメージしがちですが、実は季節を問わず起こります。高齢者、小さな子ども、体調を崩した方、さらには飲みすぎた翌朝――誰もがリスクを抱えています。
今回は、薬剤師の視点から「脱水のメカニズム」「症状」「予防と対策」を、エビデンスに基づきわかりやすく解説します。
目次
脱水はなぜ起こるのか
脱水は、体液(細胞内外の水分と電解質)が不足した状態です。原因は多岐にわたります。
- 発汗の増加(炎天下作業・運動)
- 消化器症状(下痢・嘔吐による水分・塩分喪失)
- 薬の影響(利尿薬、糖尿病治療薬)
- 摂取不足(高齢者や認知症患者では自発的飲水が減少)
特に高齢者は、口渇中枢の感度低下により「のどが渇いた」と感じにくく、症状が出た時にはすでに中等度の脱水に陥っていることもあります。
脱水の症状と重症度
軽度(体重減少率 約3%)
- のどの渇き
- 口腔乾燥
- 尿の濃縮(濃い黄色)
中等度(体重減少率 約6%)
- めまい・ふらつき
- 筋けいれん(こむら返り)
- 集中力低下・倦怠感
重度(体重減少率 約9%以上)
- 血圧低下・頻脈
- 意識障害
- 尿量減少(無尿に近い)
- 皮膚の弾力低下(皮膚ツルゴール遅延)
ポイント:高齢者や小児は重症化が早く、短時間で生命に危険が及ぶことがあります。
脱水時の応急対応
- 涼しい場所へ移動
- 衣類を緩め、体温を下げる
- 経口補水液(ORS)を少量ずつこまめに摂取
- WHO推奨ORS組成:Na⁺ 約75 mEq/L、糖濃度 75 mmol/L
- 嘔吐・意識障害がある場合は即時医療機関受診
正しい水分補給の習慣
- 起床後・入浴前後・就寝前にコップ1杯の水
- 外出時は30〜60分ごとに少量補給
- 発汗が多い場合は塩分も同時補給
- 高齢者・小児は時間を決めて飲水
カフェイン飲料やアルコールは利尿作用があり、補水には不適です。
アルコールと脱水の関係
アルコールは抗利尿ホルモン(ADH)抑制により、尿量を増やし脱水を促進します。
これが二日酔い症状(頭痛・倦怠感)の一因です。
対策
- 飲酒中は水(チェイサー)を挟む
- 就寝前に水分補給
- 翌朝は味噌汁や経口補水液でリカバリー
現場から:薬剤師が察知した脱水サイン
ある高齢患者さんが、ふらつきと傾眠傾向で来局。普段は会話もはっきりしている方です。
問診すると「水分をあまり摂っていない」と判明。病院受診で中等度脱水と診断されました。
普段との違いに気づく観察力が、薬剤師の重要な役割です。
まとめ
- 脱水は季節を問わず誰にでも起こる
- 高齢者・小児は特に注意
- 予防は「のどが渇く前に飲む」こと
- 経口補水液は正しい組成のものを選ぶ
参考文献
日本小児科学会. 下痢症に対する経口補水療法.
WHO. Oral Rehydration Salts (ORS). https://www.who.int/
厚生労働省. 熱中症関連情報. https://www.mhlw.go.jp/
日本救急医学会. 市民向け熱中症対策ガイドライン 2021.