こんにちは、『薬Talk』編集長Noriです!
さて、ある日、門前皮膚科の処方箋を眺めていたら…
「ヘパリン類似物質軟膏50g+プロペト50g、混合調剤」
という処方に遭遇。
いやいやいや、ちょっと待ってくれ、と。
「混ぜちゃうの!?」「いや別々で良くない!?」「てか、そんなにプロペト多くて大丈夫!?」
と、心の中のツッコミが止まりません。
薬局内でも新人さんから、
「これ、何のために混ぜてるんですか?何か意味あるんですか?」
と質問されがちなやつです。
というわけで今回は、「プロペト×ヘパリン類似物質軟膏」の混合処方について、
・なぜ混ぜるのか?
・混ぜたら何が良くなるのか?
・逆に、混ぜない方がいい場合って?
などなど、薬剤師目線で本音解説していきます!
目次
■ ヘパリン類似物質とプロペト、それぞれの特徴をざっくりおさらい!
| 成分名 | 特徴 | 使用感 |
|---|---|---|
| ヘパリン類似物質 | 保湿(水分保持)+血行促進作用。皮膚のターンオーバー改善にも。 | ややさっぱり |
| プロペト | 白色ワセリンの精製品。強力な保湿(油分)で水分を逃がさない。 | がっつりベタつく |
この2つ、方向性の違う保湿アプローチを持っています。
つまり、**水分を与えるタイプ(ヘパリン)+水分を閉じ込めるタイプ(プロペト)**のコンビ!
■ なぜ混ぜるの?〜皮膚科医がよく使う“うるおいチューニング”〜
皮膚科で混ぜるのは、ほぼ以下の理由から:
- ✅ 保湿力の底上げ:乾燥肌・アトピーで「ヘパリンだけじゃ足りない」場合に、プロペトの油分でロック!
- ✅ 塗り心地の調整:「プロペト単体は重たすぎるけど、混ぜれば塗りやすくなる」チューニング処方
- ✅ 時短&使いやすさ重視:「1本に混ざっていれば、患者が塗り忘れにくい」
いわばこれは、肌のためのオーダーメイド保湿ミックス。
■ 混ぜるメリット vs デメリット
| 項目 | 混ぜるメリット | 混ぜるデメリット |
|---|---|---|
| 保湿力 | 水分と油分のW保湿 | 効果調整がしにくい |
| 使用感 | ベタつき軽減・伸びやすい | 分離や変質の可能性 |
| 患者の使いやすさ | 1本にまとまり時短・忘れ防止 | 医師の意図が見えづらくなることも |
■ えっ、別々の方がいいんじゃ…?その考え、実はアリ!
以下のようなケースでは、むしろ別々処方のほうが理にかなっています👇
- 🧴 塗り分けしたい人(顔だけさっぱり、体はしっとり…など)
- ⏰ 使用タイミングを変えたい人(朝はヘパリン、夜はプロペト)
- 🧳 在宅や長期保存が必要なケース(混合品は分離リスクあり)
■ 皮膚科の現場では「当たり前の混合処方」
とくに小児のアトピー、老人性乾皮症、乾燥肌の患者さんなどにおいて、
この混合はもう**“職人芸”レベルの保湿レシピ**として定番。
医師側の処方意図としては:
- 塗り忘れ防止のために「1本にしたい」
- 市販薬と同様の感覚で使ってもらいたい
- 保湿だけじゃなく、軽い血行促進や皮膚代謝改善も加えたい
といった点が挙げられます。
- 🧴 塗り分けしたい人(顔だけさっぱり、体はしっとり…など)
- ⏰ 使用タイミングを変えたい人(朝はヘパリン、夜はプロペト)
- 🧳 在宅や長期保存が必要なケース(混合品は分離リスクあり)
■ 薬歴コメント例
混合軟膏(ヘパリン類似物質+プロペト)に関し、使用感と保湿力の両立を目的とした処方意図を説明。1日2回で継続使用を指導済。部位によりべたつきが気になる場合は別塗りで対応可能と案内。
✅ まとめ:混ぜる or 混ぜない?は処方意図と患者背景しだい
| 処方パターン | 向いているケース |
|---|---|
| 混合処方 | 時短・塗り忘れ防止・保湿強化を狙うとき |
| 別々処方 | 使用感にこだわる人・塗り分け・調整が必要なとき |
どちらにも正解があります。
大事なのは「なぜこう処方されたのか」を理解し、患者さんに合った指導ができること!
✅ 締めの文章(語りかけ口調で)
いかがでしたか?
「ヘパリン類似物質軟膏50g+プロペト50g」の混合処方、一見すると地味ですが、そこには皮膚科医の知恵とこだわりが詰まっています。
「なんで混ぜるの?」という素朴な疑問から始まり、使用感・保湿力・患者背景まで考慮されたこの“保湿カクテル”。
私たち薬剤師としても、その意図を汲み取り、適切に説明・提案できる力が求められます。
処方意図が見えると、ただの「白い軟膏」も少しだけ面白くなりますよね。
今日も調剤室の片隅で、「混ぜるか、混ぜないか」をちょっとだけ考えてみてください。
それではまた、次の記事でお会いしましょう!
『薬Talk』編集長Noriでした!
📚 参考文献
- https://www.maruho.co.jp/med/product/hirudoid/(マルホ株式会社|ヘパリン類似物質製品情報)
- https://www.kenei-pharm.com/propet/(健栄製薬|プロペト®製品情報)
- https://www.jshp.or.jp/cont/22/20220513-2.pdf(日本病院薬剤師会|混合調剤の安定性に関する資料)
- https://medical-tribune.co.jp/rensai/2020/1223539867/(Medical Tribune|皮膚科医による混合処方の臨床使用例)
- https://www.dermatol.or.jp/qa/qa29/q02.html(日本皮膚科学会|ヒルドイドに関するQ&A)
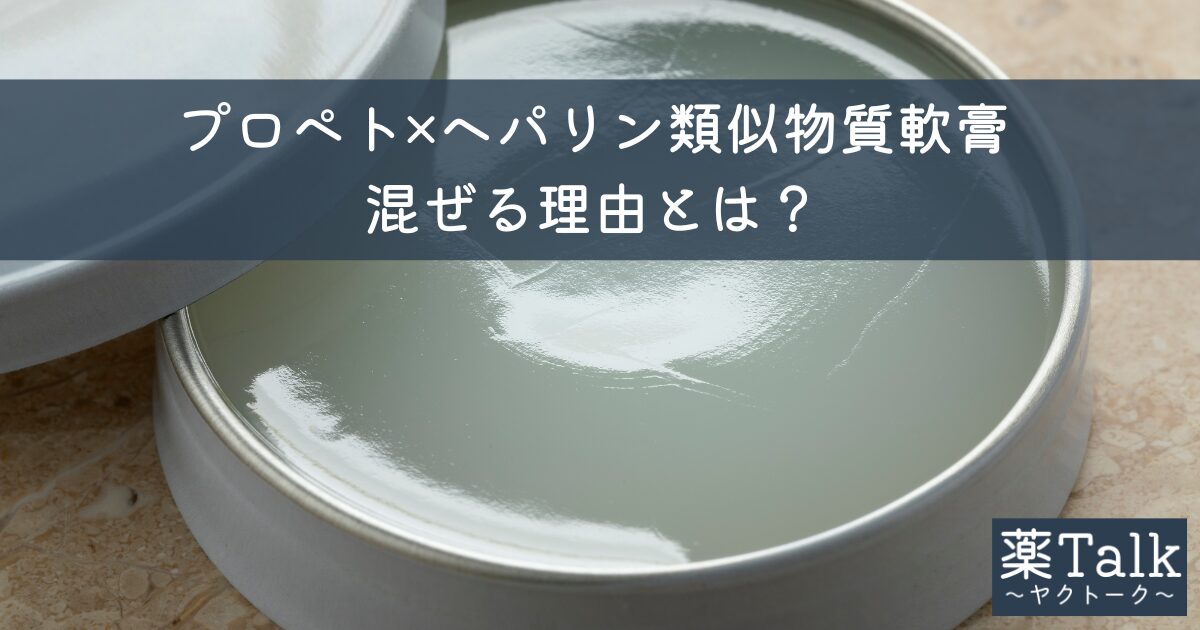

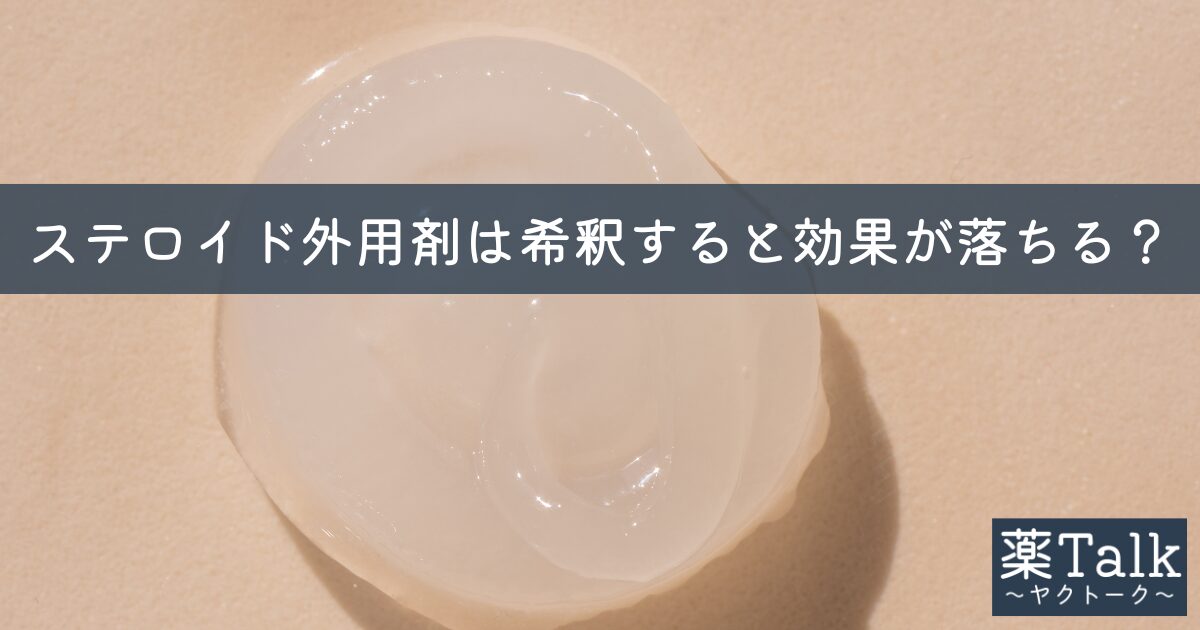
コメント この記事に対する意見・質問はこちら