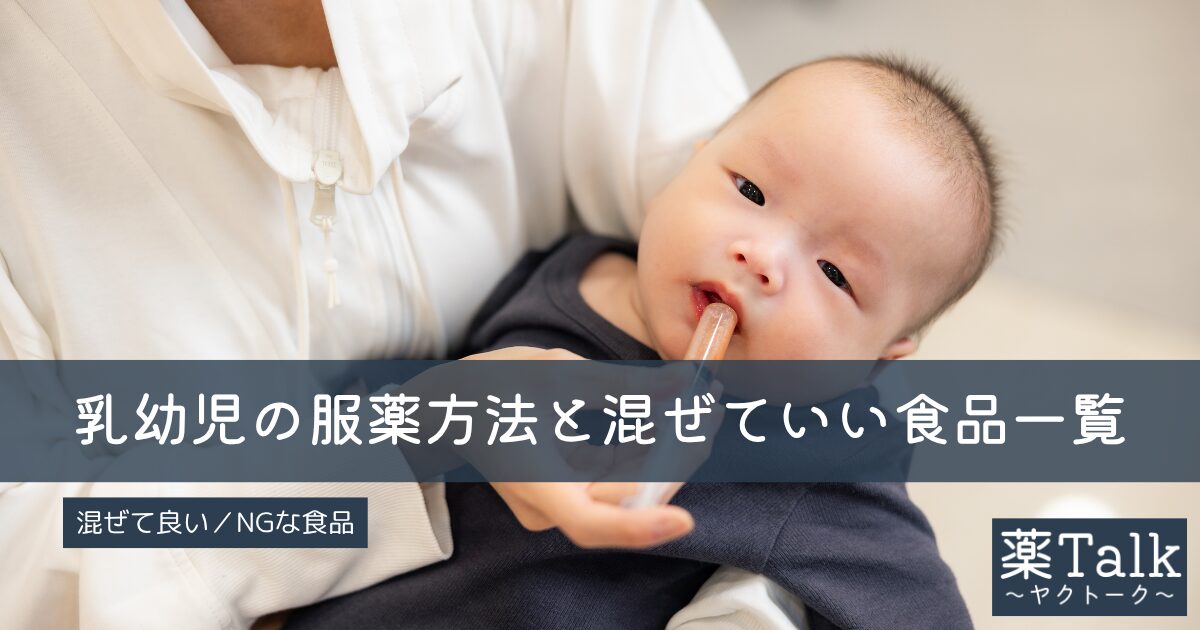こんにちは、『薬Talk』編集長、薬剤師のNoriです。
私も新人の頃、乳幼児の坐薬の順番やタイミングで悩んだ経験があります。
特に「吐き気止めと解熱剤、どっちが先?」や、「入れてすぐ出てしまったら?」など、
現場では一瞬の判断が求められますよね。
今回は、薬剤師として保護者に指導する時や、自分が調剤・説明する時に役立つよう、
坐薬の種類・基剤・順番の決め方を整理します。
難しい部分は解説を入れて、表の内容も理解しやすい形にしました。
※本記事は薬剤師の経験と公的資料をもとに作成しています。患者への使用判断は必ず医師の指示を優先してください。
目次
1. 坐薬の種類と基剤の違い
坐薬は有効成分だけでなく「基剤」が重要です。
基剤によって溶け方や吸収速度が異なり、順番や間隔の指導に直結します。
- 脂溶性基剤(例:Witepsol®)
→ 体温で溶ける。溶解後は粘膜から速やかに吸収されるが、腸内容物の影響を受けやすい。 - 水溶性基剤(例:PEG系)
→ 水分と混ざって徐々に溶ける。作用発現は脂溶性より遅め。
現場では、「ナウゼリン®(水溶性)」と「アンヒバ®(脂溶性)」を一緒に使うケースが典型例です。
| 坐薬名 | 主成分 | 基剤の種類 | 保存方法 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| アンヒバ®坐剤 | アセトアミノフェン | 脂溶性基剤(Witepsol®) | 冷所保存 | 解熱 |
| ナウゼリン®坐剤 | ドンペリドン | 水溶性基剤(PEG系) | 室温保存可 | 吐き気・嘔吐 |
| ダイアップ®坐剤 | ジアゼパム | 脂溶性基剤(Witepsol®) | 冷所保存 | 熱性けいれん予防 |
2. 坐薬の使用順序ルール
基剤の違いがあると、先に入れた薬が溶けてしまうのを防ぐため、順番と間隔に注意します。
- 基剤が異なる場合(水溶性→脂溶性):30分以上間隔をあける
- 基剤が同じ場合(脂溶性+脂溶性など):緊急度が高い薬を先に入れ、5〜10分間隔
使用例(現場の指導パターン)
| パターン | 順番 | 間隔 |
|---|---|---|
| ナウゼリン(水溶性)+アンヒバ(脂溶性) | ナウゼリン → 30分後 → アンヒバ | 30分 |
| ダイアップ(脂溶性)+アンヒバ(脂溶性) | ダイアップ → 10分後 → アンヒバ | 10分 |
| ナウゼリン(水溶性)+ダイアップ(脂溶性) | ナウゼリン → 30分後 → ダイアップ | 30分 |
💊 経験談
夜間の救急外来で、ナウゼリンとアンヒバを同時に処方されたお子さんのケース。
保護者が「一緒に入れていいですか?」と質問。
基剤の違いを説明し、吐き気止めを先に使用してから30分後に解熱剤を入れるよう指導しました。
後日「説明通りにしたら嘔吐せずに解熱できた」と感謝され、改めて基剤の理解の重要性を実感しました。
3. 坐薬と内服の効果発現時間
「坐薬=早く効く」という思い込みは要注意です。
吸収速度は薬の種類と基剤によって異なります。
| 成分名 | 剤形 | 効果発現時間(目安) |
|---|---|---|
| アセトアミノフェン | カロナール細粒(内服) | 約25分 |
| アセトアミノフェン | アンヒバ坐剤 | 約90分 |
| ドンペリドン | ナウゼリンDS(内服) | 約30分 |
| ドンペリドン | ナウゼリン坐剤 | 約60分 |
🔍 解説
脂溶性坐薬は吸収が遅くなる傾向があり、急ぎたい場合は内服の方が早いこともあります。
また、嘔吐リスクが高い場合は坐薬が有効ですが、効果発現の遅さも考慮して指導が必要です。
4. ダイアップ®坐剤のタイミング
熱性けいれん予防のダイアップ®は、体温変化に応じて使用します。
- 目安:37.5℃以上で1回目
- 8時間後に38.5℃以上で2回目
- 効果は約8時間持続
- 副作用:眠気・ふらつき(異常時は医師へ連絡)
5. 坐薬挿入のコツ(指導ポイント)
薬剤師として保護者に説明する際は、「力まず、短時間で入れる」ことを強調します。
- 手を洗い、坐薬を出す
- 丸い方を先に挿入
- 肛門を30〜60秒押さえる
- 横向き姿勢+リラックス
- 潤滑剤(ワセリン等)を使用可
- 息を吐きながら挿入すると入りやすい
まとめ
- 坐薬は基剤の違いと病状の緊急度で順番を決める
- 同じ基剤は5〜10分、異なる基剤は30分以上間隔
- 坐薬が必ずしも内服より早いわけではない
- ダイアップ®は体温変化を基準に使用
- 挿入は姿勢・潤滑剤・声かけでスムーズに